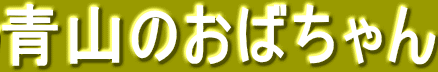 |
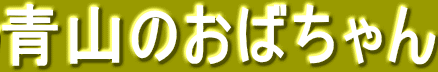 |
 |
| 三宅二三夫氏撮影 |
| その人を、私ども家族は「青山のおばちゃん」と呼んでいる。十五歳も年上だが、四十年来の友人である。和服の仕立てをするがプロ級の腕前である。そして勤め人の夫と二人でつつましくアパート暮らしをしていた。 仕立物を頼むため青山のアパートに彼女を初めて訪問した時の印象は忘れられない。ちょうど、盆おどりの頃であったのだろう、彼女は白地藍染めの浴衣を着て、かなり華やかな金と緑の市松模様の半幅帯を文庫に結んでいた。ひと踊りして来たという、やや上気した顔で袂を握り、おどりのしなを作ってみせ 「どーぉ」と笑顔を向けた。その意表をついた無邪気なしぐさが、年に似合わずなんとも愛らしかった。決して美人というわけではないし、色も黒く皺の多い顔なのだが、いたずらっぽい、くりっとした目が、晴れやかな雰囲気を漲らせていた。まさに乾坤の陽をつかさどる側の人であると思った。そのとき初対面の私も彼女の夫と顔を見合わせて、同じ笑顔を交わし、互いに打ち解けたのであった。 |
| それからは、彼女の「陽の気」に惹かれたのかも知れないが、互いに誘い合い一緒に茶会やお芝居などにも行ったりした。そんなときには和服をきりっと着て、ご自慢の西陣織正倉院裂の帯をしめ、ぽんと帯の胴をたたき気取って見せた。そこでおばちゃんの写真を撮ってあげると、とてもよろこんで、ためつすがめつ眺め自分がとてもよく撮れたと無邪気に嬉しがるのであった。 |
 |
| 三宅二三夫氏撮影 |
| その後、アパートにお邪魔したら、「待っててねー、今お茶をいれるから」と言うので、四畳半に座っていると間もなくすました顔でお盆を捧げもって入ってきた。見れば盆中に抹茶碗・棗・茶筅が乗っている。手前稽古の最も初歩の、いわゆる盆略手前のつもりなのだ。湯は魔法瓶のを使う為、しずしずと魔法瓶の前へ座った。いつぞや茶会に行ったとき、家庭でもこのようにして茶を点てたらどうかなどという話をした為か、早速実行してみたくなったらしい。これぞ正しく茶道の真髄と感じ入った。すこしうろ覚えではあったが、点て出された一碗のお薄をまことにおいしく頂戴した。茶筅は古び、棗は立派でなくとも、厚いもてなしの心が滲み出ている。それが嬉しかった。 またある時は、お雛祭りのちらし鮨を作ったから食べにいらっしゃい、と云うので伺った。「これは父の代からのお椀なの」といって底が分厚いお雛様の調度品のような朱塗金泥文のお椀に若筍の清まし汁を張り、鮨は海老・穴子・椎茸・卵・筍などが彩りよく盛られていた。八つ頭の煮物もしっくりとしたお味だったし、漬物の沢庵には細かく隠し包丁がしてあった。大変なご馳走にあずかりとても幸せであった。 |
| 彼女の最も大きな特徴と言えば、すごい倹約家であるということだ。今どきこんなことがあるのかと思われるほど切り詰めた生活をしていた。私の見るところ、まさに空前絶後、おばちゃんの右に出る人はいない。10アンペア契約の電気も、ガスや水道も基本料金以上はおそらく使っていないに違いない。夏でもクーラーはもちろん無し、窓からの風がたよりだが風のない時は、首がカタカタ震えるように廻る扇風機をつけてくれる。冬には暖房として昔のやぐら炬燵があり、それに豆炭が入っている。ずしりと重い炬燵ふとんをめくり、ごそごそと中から小さな薬缶をとりだしてきて、そのお湯でお茶を淹れてくれたのにはびっくりした。行火になっている豆炭をただ熾して置くだけでは勿体無いので、薬缶を載せて置くのだそうだ。そのやぐら炬燵は四畳半の居間にあり、そのほかに一切の暖房設備はなく、あまつさえ窓が五寸ほど開けてある。豆炭の臭いが篭るからだそうだ。それからは、冬に彼女を訪問するときは、懐炉を背負って行くことにした。 |
| 私が息子の成人記念に、お召しの着物を縫いたいと言ったら、教えてあげると言うので、懐炉を背負って彼女の家へ通ったことがあった。その着物が出来上がるばかりになって、おいとまするときに裁縫の指南料を請求されたのには驚いた。思ってもいなかったので多少うろたえた。でも考えてみればプロの仕立て屋の手を煩わせたのだから当然かもしれないと思い相当額を懐紙に挟んで差し出すと、おばちゃんは居住まいを正しうやうやしく頂き、すました顔で向きを変えて、息子の成人祝いであるといって贈られた。 包装紙でも紙袋でも新聞でも、決してただ捨てることはなく、何かに利用するべく畳んで積み上げてあるので、狭いアパートの玄関や台所は雑然としていた。散らかっているのではないのだが、何でもかんでも並べたり飾ったりして置いてある。重い玄関の金属の扉は採光性がないので、入って閉めると目が慣れず真っ暗闇で何も見えない。しばらくして、おばちゃんが10ワットぐらいの電灯を点けてくれて、やっといろいろな物が並んでいるのが見えてくる。そこをくぐるように体をはすにして、四畳半のやぐら炬燵の部屋に入れて貰うのである。私が部屋に入ればすぐに10ワットの電灯は消された。 |
 |
| 渡邊一男氏撮影 |
| おばちゃん夫婦には子がなかった。夫は実に真面目な勤め人で、会社が退けると伝書鳩のように真直ぐに帰宅する。途中どんなにおいしそうな匂いのする街角を通っても、寄り道せずひたすらおばちゃんの待っている家へ帰ってきたのだそうだ。羨ましいほど仲のよい夫婦である。退職後には夫の年金があるだろうし、彼女の生活法でゆけば、余って余ってしょうがない筈なのに、彼女はせっせとお針をして働いていた。さらに生活をこれ以上ないと思うほど無駄を省き続けて貯蓄したのである。それはやはり子がないせいであろう。わが子をはぐくむつもりで貯金を膨らませたに違いない。 しかし、やはりそれだけではない。「一円だって無駄にしてはならないのだよ」と彼女の敬慕する父に教えられ、それが彼女の生活信条となったと言っている。いかにして徹底的に無駄を省き、しかも豊かに生活できるかということを人生の目標とし、その達成に喜びを感じ、そのことが生活を貫く趣味となるまでに昇華したのではなかろうか。文字どおり趣味と実益を兼ねた張り合いのある処世法と言えよう。 花を愛で、唄を口ずさみ、時々俳句や、短歌らしきものを書き、人の情けを感じ、人に情けをかけ、義理を欠かさず、夫と仲良く暮らしている。そして自分たちでせっせと貯めた吾が子も同然のお金で人に迷惑をかけずに人生を全うすることを目標にしているのだ。 |
 |
| 嵯峨菊 三宅二三夫氏撮影 |
| 四十年の間、年に一ぺん会うかどうか分からない程度の時もあったが、年賀状は欠かさずお互いにきちんとやり取りしていた。彼女は結構筆まめなのである。日記といって大学ノートに、その日のよしなし事を段落もつけず、ぎっしりと隙間なく書いてあるのを見たことがある。行を変えると余白が無駄になるからかもしれない。 そんなおばちゃんなのに、彼女から年賀状が来なかった年があった。歳も歳だし心配になって電話をしたら元気の無い声で、おじちゃんが、腰が痛くて寝たきりになってしまい、自分は介護でふらふらに草臥れ、かねて頼んであった親戚の人にきてもらい、ここを引き払って老人ホームに移ることになった。おじちゃんはもう連れて行って貰った。自分は明日行くと言う。 |
 |
| ヤマモモ草 三宅二三夫氏撮影 |
| びっくりして、青山のアパートへ飛んでいってみた。半病人みたいになっているかと思ったが、意外に元気であった。でも背中がすっかり丸まってしまって小さく見えた。やぐら炬燵はもうなくて、代わりにハロゲンのヒーターが、赤くついていた。こんなに寒くては、病人に毒だといわれて買ったのだそうだ。「どうしても行っちゃうの?」
「うん行く」というので、互いに手をとりあって別れを惜しんだ。 |
| それから二ヶ月経ち、いきなり田舎に移ってしまった淋しさにも慣れ、落ち着いたという連絡があったので私は群馬県にあるそのホームを訪れた。日帰りのつもりだったが泊まっていってくれといわれ、折角きたのだからと、一晩お世話になることになった。ホームは立派な建物で、彼女たちのいるところは三つの部屋があって、南側は、大きく開け、関東平野が見渡せる明るい快適なところであった。青山のアパートよりずっと広くて新しい畳がまばゆかった。遠くの丘の上に目を凝らすとやっと見える程度だが、有名な観音さまの楊枝の先ほどのシルエットが望めた。横向きの角度らしくお姿のうねりが分かった。おばちゃんは、自分にはよく見えないのだが、その方角に向かって朝に晩に手を合わせているという。反対側には、上毛三山がそびえ、あの山の裾を廻ったところが彼女の故郷だと言う。 ベッドのおじちゃんにどうですかと居心地を伺うと「夢のようだよ」との返事であった。介護はおばちゃんがやらなくても夜も昼もなにくれとなく面倒をみにヘルパーさんが来てくれる。病院に入ったら、別々になってしまうが、ここではご飯も一緒に食べられる。おばちゃん夫妻は名を呼び交わしながら、いたわりあい安心して暮らしていた。 |
 |
| コスモス 渡邊一男氏撮影 |
| おばちゃん万歳!倹約を重ねて吾が子のように育てたお金が立派に役に立ったのである。帰りの車窓から見たおばちゃんのふるさとの山は、はればれと美しかった。 おわり |